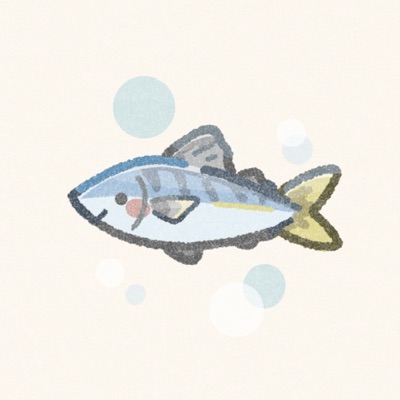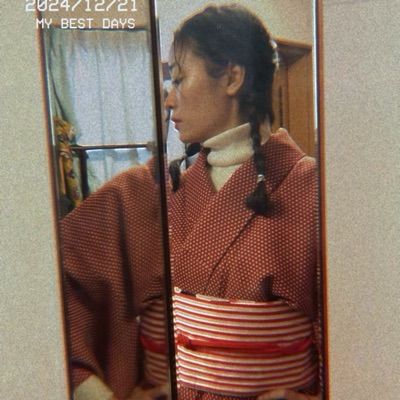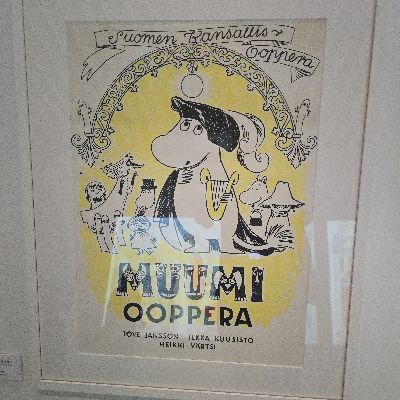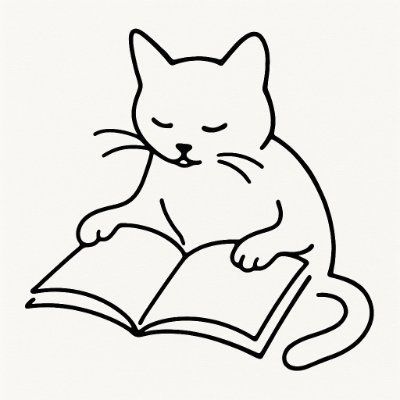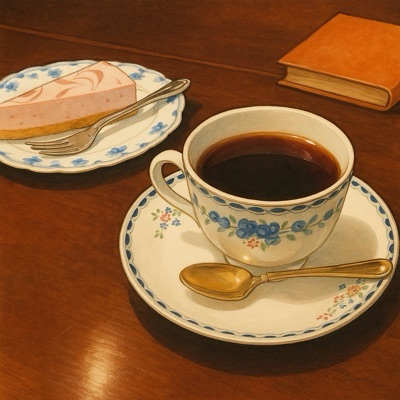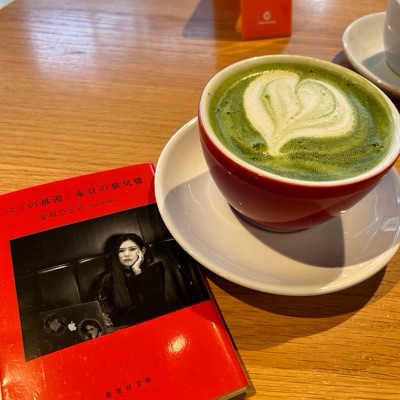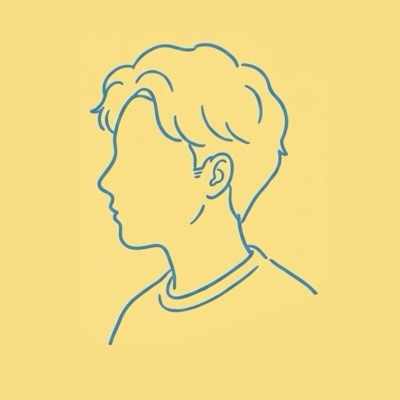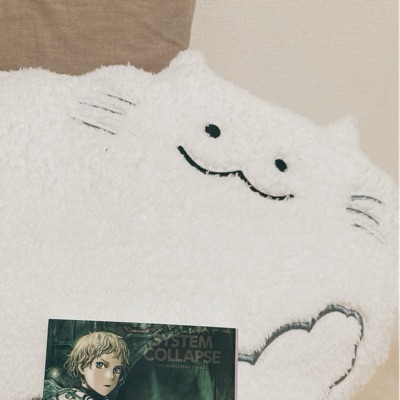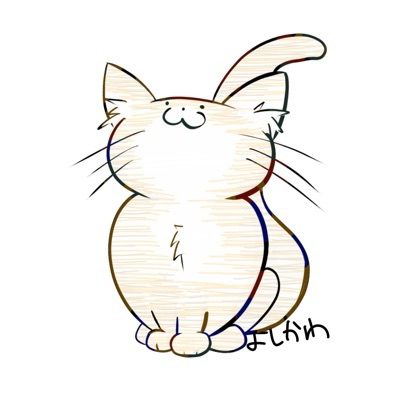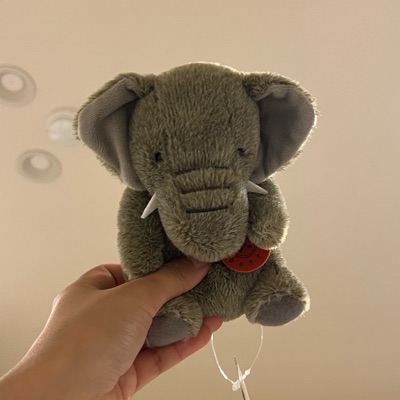「働けない」をとことん考えてみた。

275件の記録
 wakka@marui2026年1月27日読んでる途中までしか読めてないけど次の予約があるので一旦返却。 日本でマジョリティとして労働出来ないと、こんなにも苦しいのか。誰だってそこから外れる可能性があるのに。
wakka@marui2026年1月27日読んでる途中までしか読めてないけど次の予約があるので一旦返却。 日本でマジョリティとして労働出来ないと、こんなにも苦しいのか。誰だってそこから外れる可能性があるのに。
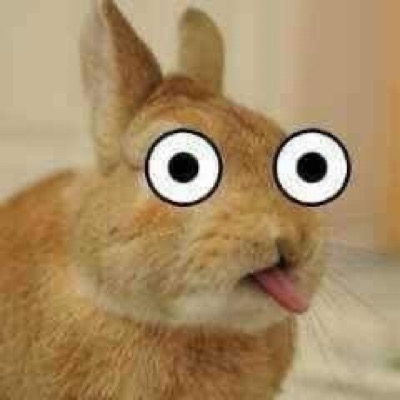
 wakka@marui2026年1月21日読んでるP45の概要 差別は人の気持ちだけでなく、制度や社会構造に起因している。 ジェンダー、障がいの有無などの差別も制度や社会構造に反映?されてしまっている。
wakka@marui2026年1月21日読んでるP45の概要 差別は人の気持ちだけでなく、制度や社会構造に起因している。 ジェンダー、障がいの有無などの差別も制度や社会構造に反映?されてしまっている。


 睡眠時間@yomuyomu2222026年1月4日読んでる読み終わった2026年1冊目。今年は本を作りながらたくさんの本を読めるように頑張りたい🥲🥲🥲 母の本棚から借りてきた1冊。 ずっと気になっていたので読めて嬉しい 正社員と呼ばれる人々がいかにマジョリティ率が高いか、そして日本の労働史がいかに女性やマイノリティに不利に作られてきたか(今なお)がわかって、それが栗田さん自身が立たされている状況や痛みとともに書かれていた 109 そして何より怠けていようが寝ていようが病んでいようが、あなたが今存在していることを否定できる人は誰もいない。いてはならない。あなたが今はただ眠ることで生き延びているならば、それはなによりも大事な営みなのだ。賃労働とは真逆であっても。
睡眠時間@yomuyomu2222026年1月4日読んでる読み終わった2026年1冊目。今年は本を作りながらたくさんの本を読めるように頑張りたい🥲🥲🥲 母の本棚から借りてきた1冊。 ずっと気になっていたので読めて嬉しい 正社員と呼ばれる人々がいかにマジョリティ率が高いか、そして日本の労働史がいかに女性やマイノリティに不利に作られてきたか(今なお)がわかって、それが栗田さん自身が立たされている状況や痛みとともに書かれていた 109 そして何より怠けていようが寝ていようが病んでいようが、あなたが今存在していることを否定できる人は誰もいない。いてはならない。あなたが今はただ眠ることで生き延びているならば、それはなによりも大事な営みなのだ。賃労働とは真逆であっても。

 たかむら@ryotakamura04272025年12月10日読み終わった働いて…と言われる中で、「働く」とは何かという根本的なことにフォーカスしながら、そもそも「普通」「労働者」という概念自体がマジョリティ前提になっていること、本来は環境やシステムや社会が原因のものが集団間の対立を導いていることなど、本当に考えさせられる1冊でした。 栗田隆子さんの著書『ハマれないまま、生きてます』(創元社)を以前読んだことがあるので、経験を通し様々な問題がつながっていることがよく分かり、「働くって何だろうな…」というモヤモヤが自分の中にもちゃんと残る(という表現が適切か分かりませんが、そんな)感じがします。
たかむら@ryotakamura04272025年12月10日読み終わった働いて…と言われる中で、「働く」とは何かという根本的なことにフォーカスしながら、そもそも「普通」「労働者」という概念自体がマジョリティ前提になっていること、本来は環境やシステムや社会が原因のものが集団間の対立を導いていることなど、本当に考えさせられる1冊でした。 栗田隆子さんの著書『ハマれないまま、生きてます』(創元社)を以前読んだことがあるので、経験を通し様々な問題がつながっていることがよく分かり、「働くって何だろうな…」というモヤモヤが自分の中にもちゃんと残る(という表現が適切か分かりませんが、そんな)感じがします。

 植月 のぞみ@nozomi_uetsuki_r4102025年11月25日積読2025年購入した本終盤まで読んでいるが、読みきらないといけない。 良い本。「働けない人」「働かない人」も権力やマジョリティからの人権侵害がなく、普通に生きられる社会を!
植月 のぞみ@nozomi_uetsuki_r4102025年11月25日積読2025年購入した本終盤まで読んでいるが、読みきらないといけない。 良い本。「働けない人」「働かない人」も権力やマジョリティからの人権侵害がなく、普通に生きられる社会を!




 紙村@kamimura_2025年10月29日読み終わったロスジェネ世代の著者が<「働かない/働けない」というテーマで、しかも「働かない/働けない女性(独身女性)」の視点から>書く労働論の本。 <あなたが今はただ眠ることで生き延びているならば、それはなによりも大事な営みなのだ。賃労働とは真逆であっても。> この一文を思い出すだけで、自分を肯定できる日があるはずだ
紙村@kamimura_2025年10月29日読み終わったロスジェネ世代の著者が<「働かない/働けない」というテーマで、しかも「働かない/働けない女性(独身女性)」の視点から>書く労働論の本。 <あなたが今はただ眠ることで生き延びているならば、それはなによりも大事な営みなのだ。賃労働とは真逆であっても。> この一文を思い出すだけで、自分を肯定できる日があるはずだ





 しらすアイス@shirasu_aisu2025年10月22日読み終わった著者のスタンスには共感するし、賛同もする。女性の立場から労働のあり方に疑問を呈する言説は圧倒的に足りていないから、書いてくれて有り難いと思う。 だけど、私には少し物足りなかった。(私は浮世離れしているしアナキズム関連の本を愛読してるから、そことのギャップかもしれない) この本は、労働に対して何の疑問も抱いていない人が疑問を持つところまでの道案内はしてくれるものの、その先まで一緒に足を踏み入れてはくれない。違和感や理不尽の底にあるものを一緒に見に行ってはくれない。 でも社会の現状に一石を投じるには、まずはここから、ということなのかも。
しらすアイス@shirasu_aisu2025年10月22日読み終わった著者のスタンスには共感するし、賛同もする。女性の立場から労働のあり方に疑問を呈する言説は圧倒的に足りていないから、書いてくれて有り難いと思う。 だけど、私には少し物足りなかった。(私は浮世離れしているしアナキズム関連の本を愛読してるから、そことのギャップかもしれない) この本は、労働に対して何の疑問も抱いていない人が疑問を持つところまでの道案内はしてくれるものの、その先まで一緒に足を踏み入れてはくれない。違和感や理不尽の底にあるものを一緒に見に行ってはくれない。 でも社会の現状に一石を投じるには、まずはここから、ということなのかも。




 yo_yohei@yo_yohei2025年10月3日読み終わった@ シンガポール著者の考えには賛同するものの、本のタイトルから推察していたのは、なぜ「働けない」とされる人たちが生み出されるのか、なぜ日本は企業で働いている人以外が蔑ろにされてしまうのか、そもそも「働けない」って何なのかと言ったことを歴史的、社会学的、哲学的に検証していく内容かなと思っていたので、正直なところ、今の自分が求めているものとは違うものでした。 企業の「人材」としては働けない人の現状を記載している本です。 でも、もちろん、面白い考察もところどころありました。例えば、「文学者や芸術家の精神不安定さを“天才の悲劇”と括って理解したつもりになっているが、その精神的不安定さは、フリーランスという収入の不安定さから来るものだったのではないか」という考察は今まで聞いたことがないものだったので非常に興味深かったです。
yo_yohei@yo_yohei2025年10月3日読み終わった@ シンガポール著者の考えには賛同するものの、本のタイトルから推察していたのは、なぜ「働けない」とされる人たちが生み出されるのか、なぜ日本は企業で働いている人以外が蔑ろにされてしまうのか、そもそも「働けない」って何なのかと言ったことを歴史的、社会学的、哲学的に検証していく内容かなと思っていたので、正直なところ、今の自分が求めているものとは違うものでした。 企業の「人材」としては働けない人の現状を記載している本です。 でも、もちろん、面白い考察もところどころありました。例えば、「文学者や芸術家の精神不安定さを“天才の悲劇”と括って理解したつもりになっているが、その精神的不安定さは、フリーランスという収入の不安定さから来るものだったのではないか」という考察は今まで聞いたことがないものだったので非常に興味深かったです。






 あんこちゃん@anko2025年9月21日読み終わった借りてきた世の中に対し、徹底的に疑問・不満を投げかけていて、納得や理解できるところはたくさんあった。けれども、全方向に不満を述べているだけの印象が残ってしまったのは読み方が悪かったからだろうか。これくらい強い言葉や感情がないと現状は変えられないのかもしれない。でもこういう考え方もありますよ〜とか、こういうやり方はどうですか〜など代替案があれば読みやすかったかなと思う。 おわりにを読んだら折り合いをつけて生きて行く現在が書かれていたのでそこは救われた。
あんこちゃん@anko2025年9月21日読み終わった借りてきた世の中に対し、徹底的に疑問・不満を投げかけていて、納得や理解できるところはたくさんあった。けれども、全方向に不満を述べているだけの印象が残ってしまったのは読み方が悪かったからだろうか。これくらい強い言葉や感情がないと現状は変えられないのかもしれない。でもこういう考え方もありますよ〜とか、こういうやり方はどうですか〜など代替案があれば読みやすかったかなと思う。 おわりにを読んだら折り合いをつけて生きて行く現在が書かれていたのでそこは救われた。






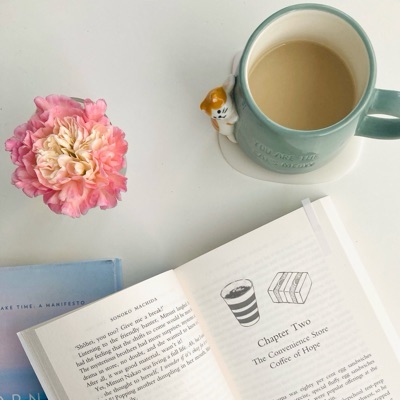

 つたゐ@tutai_k2025年9月14日読み終わったおもしろかった!「働ける」わけではないが(むしろ「働けない」が)生存できないのでなんとか「働いている」そのしんどさとか、苦しみとかに手を重ねてくれる本だと思った。読めて良かった
つたゐ@tutai_k2025年9月14日読み終わったおもしろかった!「働ける」わけではないが(むしろ「働けない」が)生存できないのでなんとか「働いている」そのしんどさとか、苦しみとかに手を重ねてくれる本だと思った。読めて良かった




 chimidori@chimidori2025年9月6日読み終わった印象的だった部分→多様性において、この社会では、安い賃金で不安定に働くあり方だけが「多様化」しただけで、模範とされるのはいまだに「正社員」「健常者成人異性愛シス男性」である
chimidori@chimidori2025年9月6日読み終わった印象的だった部分→多様性において、この社会では、安い賃金で不安定に働くあり方だけが「多様化」しただけで、模範とされるのはいまだに「正社員」「健常者成人異性愛シス男性」である





 さくら@saku_kamo_ne2025年9月2日読み終わった「正」規雇用じゃない、非正規雇用やフリーランスの人が感じる “働いているのに、働いてない感” が伝わってきた。 ちゃんとした社会人って何だろう、、って考えさせられた。 《読了》
さくら@saku_kamo_ne2025年9月2日読み終わった「正」規雇用じゃない、非正規雇用やフリーランスの人が感じる “働いているのに、働いてない感” が伝わってきた。 ちゃんとした社会人って何だろう、、って考えさせられた。 《読了》






 1neko.@ichineko112025年8月24日読み終わった「働かないおじさん」大量摂取その4 「働かない」(働けない)と「おじさん」(以外)のフレームで「働かないおじさん」を拡張認知! (楽しいぞ、この感覚!) 紹介されていたので、読みたい本(既読再読含) ☑︎「ポトスライムの船」津村記久子さん著 ☑︎「コンビニ人間」村田沙耶香さん著 □「コークスが燃えている」櫻木みわさん著 □「介護者D」阿﨑秋子さん著 □「景品」星新一さん著 割と凄く、世の中のポイント系制度設計が 大嫌いなので、割と直ぐに読みたい。
1neko.@ichineko112025年8月24日読み終わった「働かないおじさん」大量摂取その4 「働かない」(働けない)と「おじさん」(以外)のフレームで「働かないおじさん」を拡張認知! (楽しいぞ、この感覚!) 紹介されていたので、読みたい本(既読再読含) ☑︎「ポトスライムの船」津村記久子さん著 ☑︎「コンビニ人間」村田沙耶香さん著 □「コークスが燃えている」櫻木みわさん著 □「介護者D」阿﨑秋子さん著 □「景品」星新一さん著 割と凄く、世の中のポイント系制度設計が 大嫌いなので、割と直ぐに読みたい。







 くりこ@kurikomone2025年8月24日読み終わった「働けない」(と言っても私より全然働いてるが)という周縁化された立場から、社会の当たり前となってることを鋭く切り込んでて、気付かされることが多かった。私も「働けない」し、栗田さんと同じく持病があるし、女性だし、と周縁化された人間だけど、「当たり前」「仕方ない」と流されてしまってるなと痛感した。 たまに聖書やシモーヌヴェーユの話が挟まれるのも私好みで良い!
くりこ@kurikomone2025年8月24日読み終わった「働けない」(と言っても私より全然働いてるが)という周縁化された立場から、社会の当たり前となってることを鋭く切り込んでて、気付かされることが多かった。私も「働けない」し、栗田さんと同じく持病があるし、女性だし、と周縁化された人間だけど、「当たり前」「仕方ない」と流されてしまってるなと痛感した。 たまに聖書やシモーヌヴェーユの話が挟まれるのも私好みで良い!






 くりこ@kurikomone2025年8月23日まだ読んでる第4章 「怠け者」列伝 印象に残ったこと いわゆる「怠け者」として生きてきた人は全員男性しかおらず、(イエスやブッダ、太宰治、坂口安吾などなど、、)、女性で働かない人となると女王様、お姫様、愛人など、階級制と家父長制に支えられ賃労働が免除される。マジョリティは社会に貢献することを期待されているため、そこから外れてアウトサイダーとして生きるギャップが意味あるものと刻まれる(女性を含むマイノリティはそのギャップが存在しない) ーーーー 私は坂口恭平の生き方を尊敬しているのだけど、彼が、賃労働そっちのけで、畑したり、編み物したりと自分のオリジナルのタイムラインで生きていることは彼が、日本人/シス男性だから余計に賞賛されるのだろう。 特に彼が不倫をしているという発言(今はどうか知らないが)をしてもファンがつき続けることは、彼の何事にも縛られない振る舞いが「ギャップ」となり、より皆の支持を得られるのだと思う。女性がおんなじことしても、あそこまでの人気は出ないと思う。
くりこ@kurikomone2025年8月23日まだ読んでる第4章 「怠け者」列伝 印象に残ったこと いわゆる「怠け者」として生きてきた人は全員男性しかおらず、(イエスやブッダ、太宰治、坂口安吾などなど、、)、女性で働かない人となると女王様、お姫様、愛人など、階級制と家父長制に支えられ賃労働が免除される。マジョリティは社会に貢献することを期待されているため、そこから外れてアウトサイダーとして生きるギャップが意味あるものと刻まれる(女性を含むマイノリティはそのギャップが存在しない) ーーーー 私は坂口恭平の生き方を尊敬しているのだけど、彼が、賃労働そっちのけで、畑したり、編み物したりと自分のオリジナルのタイムラインで生きていることは彼が、日本人/シス男性だから余計に賞賛されるのだろう。 特に彼が不倫をしているという発言(今はどうか知らないが)をしてもファンがつき続けることは、彼の何事にも縛られない振る舞いが「ギャップ」となり、より皆の支持を得られるのだと思う。女性がおんなじことしても、あそこまでの人気は出ないと思う。




 くりこ@kurikomone2025年8月22日まだ読んでるp.116 在宅ワークが普及され働く時間を減らそうと言われているにも関わらず、フルタイムで週五回働けるのが当たり前の体力の持ち主、心身の影響を受けない人をいまだに労働者モデルに据えている社会が、労働のハードルを上げ、生産力が頭打ちにさせているのではないかという指摘には深く頷ける。ここは、第二章の、生活保護や障害者手帳を持つ人を怠けている、ずるい、本人の性格の問題だとバッシングすることと繋がる。 あと、栗田さんはシモーヌヴェーユの研究をしていただけあり、「不幸があまりに大きすぎると人間は同情すらしてもらえない。嫌悪され恐ろしがられ軽蔑される」というヴェイユの言葉が、上記バッシングを暗示していると指摘している。 ヴェイユの『重力と恩寵』をここに繋げてくるのが栗田さん独特の考察力で面白い。
くりこ@kurikomone2025年8月22日まだ読んでるp.116 在宅ワークが普及され働く時間を減らそうと言われているにも関わらず、フルタイムで週五回働けるのが当たり前の体力の持ち主、心身の影響を受けない人をいまだに労働者モデルに据えている社会が、労働のハードルを上げ、生産力が頭打ちにさせているのではないかという指摘には深く頷ける。ここは、第二章の、生活保護や障害者手帳を持つ人を怠けている、ずるい、本人の性格の問題だとバッシングすることと繋がる。 あと、栗田さんはシモーヌヴェーユの研究をしていただけあり、「不幸があまりに大きすぎると人間は同情すらしてもらえない。嫌悪され恐ろしがられ軽蔑される」というヴェイユの言葉が、上記バッシングを暗示していると指摘している。 ヴェイユの『重力と恩寵』をここに繋げてくるのが栗田さん独特の考察力で面白い。




 さくら@saku_kamo_ne2025年8月20日読み始めた「働きたくないのか働けないのか煮え切らぬ心性のまま、仕事をし、仕事に距離がある……とはいえもしかしたら多くの人がそんな思いで仕事をしているかもしれない」p.5 仕事をすることが当たり前の社会で、「なぜ働くのだろう」と考えるのは、おかしなことなのかもしれない。 社会人として当然だとか、生きるためには必要なことだろうとか、そいういう話じゃないと思うんだ。 読み進めるのが楽しみ!
さくら@saku_kamo_ne2025年8月20日読み始めた「働きたくないのか働けないのか煮え切らぬ心性のまま、仕事をし、仕事に距離がある……とはいえもしかしたら多くの人がそんな思いで仕事をしているかもしれない」p.5 仕事をすることが当たり前の社会で、「なぜ働くのだろう」と考えるのは、おかしなことなのかもしれない。 社会人として当然だとか、生きるためには必要なことだろうとか、そいういう話じゃないと思うんだ。 読み進めるのが楽しみ!
 くりこ@kurikomone2025年8月19日まだ読んでる栗田さんの鋭い指摘に頷きながら読む 77ページ ダイバーシティとは企業における人材のダイバーシティなので、ジェントリフィケーションでホームレスを排除してもなんら矛盾しない 90ページ 早稲田の渡部直己のセクハラに言及し、仕事をしてる中でハラスメントを行うということは労働の対価ではあるはずの賃金がハラスメントにも支払われている 106ページ 職場での横領、賄賂、癒着、ハラスメントより怠けている人に対する視線が冷たい。
くりこ@kurikomone2025年8月19日まだ読んでる栗田さんの鋭い指摘に頷きながら読む 77ページ ダイバーシティとは企業における人材のダイバーシティなので、ジェントリフィケーションでホームレスを排除してもなんら矛盾しない 90ページ 早稲田の渡部直己のセクハラに言及し、仕事をしてる中でハラスメントを行うということは労働の対価ではあるはずの賃金がハラスメントにも支払われている 106ページ 職場での横領、賄賂、癒着、ハラスメントより怠けている人に対する視線が冷たい。



 くりこ@kurikomone2025年8月18日まだ読んでる私自身病気で働けないので読んでみた。第二章の障害年金の制度の不透明さが、制度的レイシズム(差別は人の気持ちや憎悪だけの話だけではない…制度やその制度が構築しているシステムといった社会構造に起因している)であるというのは深く頷ける。 栗田さんは日本年金機構や年金事務所への抗議電話ん、体調が悪くて布団で寝ながらしてたと書かれていた。 布団の中からでも勉強会をしたりこの事態を変えるアクションを起こしたい、と書かれてて励まされた(まさに『布団の中から蜂起せよ』!) ——————- p.76 日本社会においてはダイバーシティと言ったところで、絶対にそこには含まれない人が一定数いるのはなぜなのかと以前から思っていたが、これを読んで納得した。あくまで企業に貢献できる人材としての多様性であって、家庭や学校、あるいは地域や国家における多様性という話ではないのである。
くりこ@kurikomone2025年8月18日まだ読んでる私自身病気で働けないので読んでみた。第二章の障害年金の制度の不透明さが、制度的レイシズム(差別は人の気持ちや憎悪だけの話だけではない…制度やその制度が構築しているシステムといった社会構造に起因している)であるというのは深く頷ける。 栗田さんは日本年金機構や年金事務所への抗議電話ん、体調が悪くて布団で寝ながらしてたと書かれていた。 布団の中からでも勉強会をしたりこの事態を変えるアクションを起こしたい、と書かれてて励まされた(まさに『布団の中から蜂起せよ』!) ——————- p.76 日本社会においてはダイバーシティと言ったところで、絶対にそこには含まれない人が一定数いるのはなぜなのかと以前から思っていたが、これを読んで納得した。あくまで企業に貢献できる人材としての多様性であって、家庭や学校、あるいは地域や国家における多様性という話ではないのである。




 Kanata@150philosophy2025年7月1日読み終わった社会的弱者に向けられるバッシングは単に弱い者虐めであり何の合理性もない バッシングする人自身に解決すべき問題があるが、その問題は自覚されておらず、さらにその一因は構造的なもので、本来バッシングを向けられるべき既得権益層、搾取している層は誹りを免れる不条理を思った
Kanata@150philosophy2025年7月1日読み終わった社会的弱者に向けられるバッシングは単に弱い者虐めであり何の合理性もない バッシングする人自身に解決すべき問題があるが、その問題は自覚されておらず、さらにその一因は構造的なもので、本来バッシングを向けられるべき既得権益層、搾取している層は誹りを免れる不条理を思った

 白玉庵@shfttg2025年6月30日読み終わった「弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く」から抜け出して、社会構造に目を向けていきましょう。そのヒントがたくさん載っています。 P202 「活」のつく言葉は怪しい、というところに激しく膝を叩いたので、『生きるためのフェミニズム』も読んでみます。 ヴェイユと深沢七郎、いいよなぁ。
白玉庵@shfttg2025年6月30日読み終わった「弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く」から抜け出して、社会構造に目を向けていきましょう。そのヒントがたくさん載っています。 P202 「活」のつく言葉は怪しい、というところに激しく膝を叩いたので、『生きるためのフェミニズム』も読んでみます。 ヴェイユと深沢七郎、いいよなぁ。




 imo@imoimo2025年6月4日読み終わった生活の中で「え?これでは私の暮らしは何も良くならないんだけど?何で他の人は不満じゃないんだろう」と感じる時が多くある そういう時「あなたは人間のうちに含まれていません」というメッセージを感じる この私の感じ方はオーバーかもしれないけど、「あなたはこの暮らしを良くする制度の対象ではないですので」と言われているように感じている人が他にもいると知れて少し安心した あと体調不良の時に自責してしまうのは、自分の場合、自己コントロール感の欠如に起因するのかなぁと読んでいて思った。 筆者と似た状況で生きて、似た考えを持っているけど、日常では孤立感を感じる場面が多い 周囲に裕福な人が多いわけでもないのに、清貧を良しとしている感じ 皆大変なんだったら皆でちょっとずつ楽にしていきましょうよ、疑問を持って意見を言うの、皆でやっていきたいよ、と思う こういう本が広く読まれてほしい
imo@imoimo2025年6月4日読み終わった生活の中で「え?これでは私の暮らしは何も良くならないんだけど?何で他の人は不満じゃないんだろう」と感じる時が多くある そういう時「あなたは人間のうちに含まれていません」というメッセージを感じる この私の感じ方はオーバーかもしれないけど、「あなたはこの暮らしを良くする制度の対象ではないですので」と言われているように感じている人が他にもいると知れて少し安心した あと体調不良の時に自責してしまうのは、自分の場合、自己コントロール感の欠如に起因するのかなぁと読んでいて思った。 筆者と似た状況で生きて、似た考えを持っているけど、日常では孤立感を感じる場面が多い 周囲に裕福な人が多いわけでもないのに、清貧を良しとしている感じ 皆大変なんだったら皆でちょっとずつ楽にしていきましょうよ、疑問を持って意見を言うの、皆でやっていきたいよ、と思う こういう本が広く読まれてほしい





 読谷 文@fumi_yomitani2025年5月30日読み終わったすごくよかった。タイトル通り「働けない」側の視点から見た現在の日本の労働問題の歪さを真摯に問うている本だった。 氷河期世代で、働いたり働けなかったりした経験を持つ者として、大いに頷きながら読んだ。 現在三刷とのことで、共感する人がたくさんいるのだろうと思う。 ・「週5日フルタイムで出勤・残業を厭わない」働き方が当然のように基準とされ、 それに基づいて法律・税制・年金制度がつくられており、その働き方の基準から少しでも外れると、あっという間に「いない存在」とみなされる。 ・「多様性」や「女性活躍」という言葉が意図するのはあくまで「企業内で役立つ人材」においてであって、その他の生活の場面でのマイノリティを指している訳ではない。 ・この社会では「賃労働」のみが「働く」ことを意味していて、生きていくのに必須な労働である「育児」や「介護」は「休暇」とみなされる。 などなど、ここに全ては書ききれないくらい、今までモヤモヤしていた事象に対して「おかしくない?」とひとつひとつ問うてゆく著者の姿勢に、胸打たれ共感の嵐だった。 また本文中で紹介されていた、テネシー・ウィリアムズの「ガラスの動物園」や、シモーヌ・ヴェイユ、森茉莉、深沢七郎、星新一など、読んでみたいと思う作品がたくさんあったし、著者の別の作品も是非読みたいと思った。
読谷 文@fumi_yomitani2025年5月30日読み終わったすごくよかった。タイトル通り「働けない」側の視点から見た現在の日本の労働問題の歪さを真摯に問うている本だった。 氷河期世代で、働いたり働けなかったりした経験を持つ者として、大いに頷きながら読んだ。 現在三刷とのことで、共感する人がたくさんいるのだろうと思う。 ・「週5日フルタイムで出勤・残業を厭わない」働き方が当然のように基準とされ、 それに基づいて法律・税制・年金制度がつくられており、その働き方の基準から少しでも外れると、あっという間に「いない存在」とみなされる。 ・「多様性」や「女性活躍」という言葉が意図するのはあくまで「企業内で役立つ人材」においてであって、その他の生活の場面でのマイノリティを指している訳ではない。 ・この社会では「賃労働」のみが「働く」ことを意味していて、生きていくのに必須な労働である「育児」や「介護」は「休暇」とみなされる。 などなど、ここに全ては書ききれないくらい、今までモヤモヤしていた事象に対して「おかしくない?」とひとつひとつ問うてゆく著者の姿勢に、胸打たれ共感の嵐だった。 また本文中で紹介されていた、テネシー・ウィリアムズの「ガラスの動物園」や、シモーヌ・ヴェイユ、森茉莉、深沢七郎、星新一など、読んでみたいと思う作品がたくさんあったし、著者の別の作品も是非読みたいと思った。









 TOMOCK@To_mock2025年5月28日買った読み終わった読み終わりました。終わりの方で働かないの系譜は男性ばかりというところ、本当にそうだよね。生産性のない暮らしを送りたい。毎日そう思ってます。働けない、働きたくない、働かない。いろんなグラデーションはあれど、もう少し労働者を大切に出来ないのかな、と読みながらずっとこの国の在り方のおかしさについて考えていました。
TOMOCK@To_mock2025年5月28日買った読み終わった読み終わりました。終わりの方で働かないの系譜は男性ばかりというところ、本当にそうだよね。生産性のない暮らしを送りたい。毎日そう思ってます。働けない、働きたくない、働かない。いろんなグラデーションはあれど、もう少し労働者を大切に出来ないのかな、と読みながらずっとこの国の在り方のおかしさについて考えていました。

 TOMOCK@To_mock2025年5月25日買った読んでる図書館で借りて、読みきれずこれもまた自分に必要ということで購入した本。 働けないさまざまな理由がわたしにすごく刺さる。 そうそう、そうなんだよ!の連続。 本当に働くの難しい。 と思いながら数少ない出勤をしています。。(具合はすこぶる悪い)
TOMOCK@To_mock2025年5月25日買った読んでる図書館で借りて、読みきれずこれもまた自分に必要ということで購入した本。 働けないさまざまな理由がわたしにすごく刺さる。 そうそう、そうなんだよ!の連続。 本当に働くの難しい。 と思いながら数少ない出勤をしています。。(具合はすこぶる悪い)



 ヒナタ@hinata6251412025年4月30日読み終わった生産性を求めるくせに長期的かつ論理的な視点がないから生産性は上がらずそれを根性論でなんとかしたい、人権のことは考えたくない、というのがこの国の基本メンタリティだと思うのだけど、それゆえに働けなくなる人が増え現場は人が足りずますます労働が過酷になる、という負のループが永遠に終わらない。 この本に書かれてることは、わたしはそんなに驚くことなく、そうですよねとうんうん頷くばかりだったのだけど、国や会社の意思決定の場にいる人たちには見えてない現実かもしれないので、そういう人たちにこそぜひ読んでほしいと思った。でもタイトルを見ただけで怒り出しそう笑
ヒナタ@hinata6251412025年4月30日読み終わった生産性を求めるくせに長期的かつ論理的な視点がないから生産性は上がらずそれを根性論でなんとかしたい、人権のことは考えたくない、というのがこの国の基本メンタリティだと思うのだけど、それゆえに働けなくなる人が増え現場は人が足りずますます労働が過酷になる、という負のループが永遠に終わらない。 この本に書かれてることは、わたしはそんなに驚くことなく、そうですよねとうんうん頷くばかりだったのだけど、国や会社の意思決定の場にいる人たちには見えてない現実かもしれないので、そういう人たちにこそぜひ読んでほしいと思った。でもタイトルを見ただけで怒り出しそう笑





 うえの公園@uenopark2025年4月7日読み終わったこれを読んで保守的な政党を応援している人、なんとなく投票している人が減り、生活に寄り添った政党を応援するようになってほしい。制度は変えられる!
うえの公園@uenopark2025年4月7日読み終わったこれを読んで保守的な政党を応援している人、なんとなく投票している人が減り、生活に寄り添った政党を応援するようになってほしい。制度は変えられる!



 親知らず抜いた@y_sa2025年3月30日読み終わった「怠けていると言いたくなるとき、むしろ問うべきはそんなふうに人をくさしたくなるほど嫌なことをしなければならない状況や環境だ。」 「いつまでも楽にならない労働。楽になってはいけないと思い込まされている労働。それこそかつてのアメリカとの戦争で、本土決戦にそなえて竹槍訓練を行い、「一億玉砕」というお題目で勝てない相手に体当たりして死ぬことをよしとする価値観、つまり無意味であっても「努力」し、自己犠牲で、集団に染まって思考停止することを良しとする価値観がいまもなお「労働」の名の下にはびこっているように思えてならないのだ。」
親知らず抜いた@y_sa2025年3月30日読み終わった「怠けていると言いたくなるとき、むしろ問うべきはそんなふうに人をくさしたくなるほど嫌なことをしなければならない状況や環境だ。」 「いつまでも楽にならない労働。楽になってはいけないと思い込まされている労働。それこそかつてのアメリカとの戦争で、本土決戦にそなえて竹槍訓練を行い、「一億玉砕」というお題目で勝てない相手に体当たりして死ぬことをよしとする価値観、つまり無意味であっても「努力」し、自己犠牲で、集団に染まって思考停止することを良しとする価値観がいまもなお「労働」の名の下にはびこっているように思えてならないのだ。」


- さみ@futatabi2025年3月20日読んでる・会社でインボイス制度の説明を受けた時よりわかりやすかった……し、「何回読んでもわからない説明」の「何回読んでもわからなさ」に悪意と無関心が込められている可能性がある、ということに思い当たる助けになる ・◯◯休暇について「育児や介護は睡眠時間を削られ、一瞬も相手から目を離せず、ただ休んでいるわけではない。〜出産や育児、そして介護を『休暇』として考えるのは、賃労働のみを仕事と捉え、〜」本当にそうだ、考えてみれば(考える、という思考に至らず文字通り受け止めていた)言葉が実態と合っていないしそのせいで不要な分断を生んでいるように思う




 あずき(小豆書房)@azukishobo2025年3月12日紹介労働をとりまく歪な構造。読んでいると、「普通」 というものは、そう思い込んで(もしくは思い込まされて)いるものに過ぎないと気づく。だから制度に当てはめると、必ずどこかで無理が生じる。 制度は必要。だけど、その欠陥についても認識しておくことがとても大切だと思う。
あずき(小豆書房)@azukishobo2025年3月12日紹介労働をとりまく歪な構造。読んでいると、「普通」 というものは、そう思い込んで(もしくは思い込まされて)いるものに過ぎないと気づく。だから制度に当てはめると、必ずどこかで無理が生じる。 制度は必要。だけど、その欠陥についても認識しておくことがとても大切だと思う。

 雨晴文庫@amehare_bunko20232025年3月8日読み終わった読書日記いつも付箋だらけになる栗隆さんの新刊。 地元のジュンク堂さんでは労働論のコーナーにひっそりと置かれていた。ファンとしては「もっと目立つところに置いてーー」と言いたい。確かに帯には”あたらしい労働論”と書いてあるけれども。 働かない、働けない、働きたくない…について語るこの本を必要としている人が労働論の棚を覗く可能性はおそらくかなり低い。 “日本社会においてはダイバーシティと言ったところで、絶対にそこには含まれない人が一定数いるのはなぜなのかと以前から思っていたが…(中略)あくまで企業に貢献できる人材としての多様性であって、家庭や学校、あるいは地域や国家における多様性という話ではないのである。” p76より この記述の後に、同性のパートナーシップ条例はいち早く導入しつつ、ホームレスの人たちを予告なく排除するなどの渋谷区の動きを例に挙げている。 “多様性”が、人びとの生きやすさではなく社会の”生産性”を上げる文脈に回収されてしまいやすい傾向にはほんとうに辟易する。 「南の島のハメハメハ大王」の歌について、その根底にある勤勉性に対する絶対的な評価と、そうでない人への蔑視を指摘しつつ、 ”風が吹いたら遅刻して雨が降ったら休みながらもどうにか生きたり働けたり学べたりできないか。しかもそれが周縁的な立場というより、ど真ん中に存在しているものとして労働制度やシステムや価値観を組み直せないか。それは長年の私の悲願と言っていい。“ という。 気圧や気候変動に人一倍弱く体調を崩すわたしは、この主張に完全に同意する。 そしてそれが叶えば、いま、一切働けないでいる人のある程度が働ける可能性に開かれると確信する。 『ぼそぼそ声のフェミニズム』とともに、読んだ人と感想を語り合いたくなる本。
雨晴文庫@amehare_bunko20232025年3月8日読み終わった読書日記いつも付箋だらけになる栗隆さんの新刊。 地元のジュンク堂さんでは労働論のコーナーにひっそりと置かれていた。ファンとしては「もっと目立つところに置いてーー」と言いたい。確かに帯には”あたらしい労働論”と書いてあるけれども。 働かない、働けない、働きたくない…について語るこの本を必要としている人が労働論の棚を覗く可能性はおそらくかなり低い。 “日本社会においてはダイバーシティと言ったところで、絶対にそこには含まれない人が一定数いるのはなぜなのかと以前から思っていたが…(中略)あくまで企業に貢献できる人材としての多様性であって、家庭や学校、あるいは地域や国家における多様性という話ではないのである。” p76より この記述の後に、同性のパートナーシップ条例はいち早く導入しつつ、ホームレスの人たちを予告なく排除するなどの渋谷区の動きを例に挙げている。 “多様性”が、人びとの生きやすさではなく社会の”生産性”を上げる文脈に回収されてしまいやすい傾向にはほんとうに辟易する。 「南の島のハメハメハ大王」の歌について、その根底にある勤勉性に対する絶対的な評価と、そうでない人への蔑視を指摘しつつ、 ”風が吹いたら遅刻して雨が降ったら休みながらもどうにか生きたり働けたり学べたりできないか。しかもそれが周縁的な立場というより、ど真ん中に存在しているものとして労働制度やシステムや価値観を組み直せないか。それは長年の私の悲願と言っていい。“ という。 気圧や気候変動に人一倍弱く体調を崩すわたしは、この主張に完全に同意する。 そしてそれが叶えば、いま、一切働けないでいる人のある程度が働ける可能性に開かれると確信する。 『ぼそぼそ声のフェミニズム』とともに、読んだ人と感想を語り合いたくなる本。


 本を閉じた。地球だった。@rousoku2025年3月8日読み始めた正規雇用の「正」ってなんだよって読んで初めて気がつきました。正規雇用の「正」ってなんだろう。この社会が悪いことはもう重々承知していますが、そのあとどうすればいいのかはイマイチ分かっていません。
本を閉じた。地球だった。@rousoku2025年3月8日読み始めた正規雇用の「正」ってなんだよって読んで初めて気がつきました。正規雇用の「正」ってなんだろう。この社会が悪いことはもう重々承知していますが、そのあとどうすればいいのかはイマイチ分かっていません。